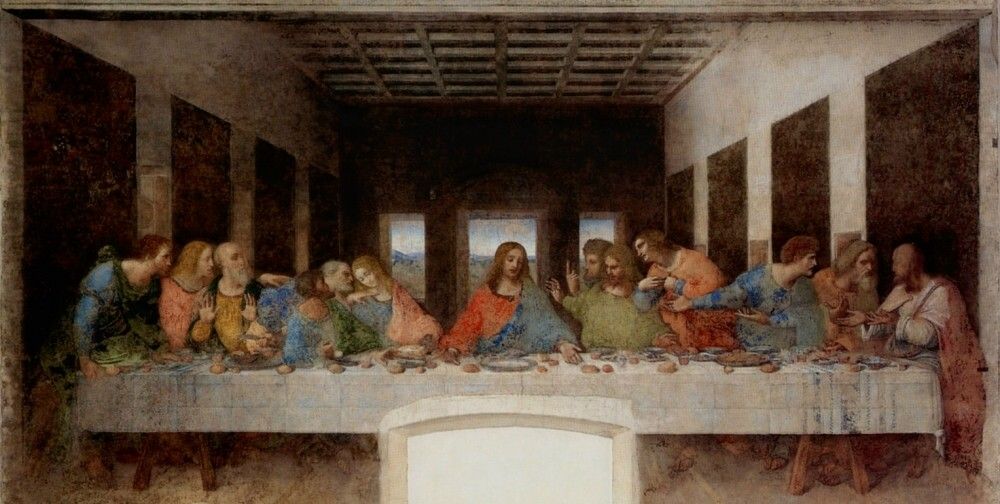儒教は宗教なのか、という疑問はあるだろう。
宗教であるようで宗教ではないような、儒教は不思議な姿をしている。儒教は宗教であるか、宗教でないかの境界線に立っているといえるのではないだろうか。逆にいうと境界線に立っているから、宗教のもつ本質が顕わになってしまうのではないだろうか。
儒教ほど権力と癒着した宗教はないだろう。いや、癒着というのではない。権力の維持と安定化を目的にした宗教だといえる。境界線に立っているから、意図的か非意図的かということを無視していえば、宗教が担っている目的を隠しようがなくなるのかもしれない。
儒教が権力の維持と安定化を目的とした宗教だとすると、初めに宗教ありきではないことになる。そして当然に原初としての宗教的な心もないことになる。儒教という宗教は目的ではなく手段だったといえると思うが、儒教以外の宗教もまた権力に利用される形で、儒教と同じ目的を担うことになるといえるのではないだろうか。だから宗教は権力と癒着し、自らもまた権力の権化にまで堕落するのだろう。
儒教は厳格な身分制を敷いて、その身分に応じた道徳を生きることを説くわけであるが、宗教の装いをその道徳に凝らしているのだろう。宗教の装いをせずに剥き出しにすると、厳格な身分制だけが際立ち、当然に反発を招くことになる。宗教の装いをすることで、身分制をすんなりと受け入れさせ、更にその身分制を社会の隅々にまで構造化させるような力を道徳に忍ばせているのだろう。そうして社会に安定をもたらし、結果的に体制の維持と強化につなげようとする目的があるのだろう。
こうした儒教的社会は考えて見れば、権力にとっては好ましいものであっても、必ずしも民衆にとっては好ましいものとはいえないはずだ。が、身分制とは社会的な関係性でありながら、個人と個人との関係性でもあるので、家の中にまで関係性が持ち込まれることになる。そしてその関係性が道徳によって飾り立てられているから単純ではない。家父長が妻と子供を隷属的に支配することが、道徳によって巧妙に正当化される。だから身分的権力構造が隅々まで貫徹されていくのである。家の中にまで身分制が息づき、その身分制的関係性が道徳の名で美化されながら日常化するのだから、儒教的身分制の日常を生きた子供が大人になれば、その関係性を再生産することになるのだろう。
しかし、儒教道徳が人の心の内奥まで操っているかというと甚だ疑問である。
わたしは道徳によって人の心の内奥にある情動が表面に出てこないように、蓋をして押さえつけているだけではないかと思う。心の奥底にある情動までも儒教の身分制的道徳では操縦はできないと知っているから、儒教社会は儀礼を重んじる社会になるのではないだろうか。つまり人の心の内奥までの支配を射程に入れていないから、表面的な儀礼を日常の中に徹底させ習慣化させることで、儒教的な身分制と社会的関係性を持続させようとするのである。儒教は目上の者に対する接し方や挨拶の仕方、またお辞儀の仕方や言葉遣いといった儀礼を重視し、細微に渡って道徳としての作法と生き方が強要され、徹底的に叩き込まれるのだろう。
が、表面上は儀礼に忠実だとしても、深々とお辞儀をながら、心の中では舌を出しているとも限らないのである。儒教が宗教かどうかの境界線に立っているのは、人の心の奥底で舌を出す情動までは操縦(=洗脳)できないという事情によるのではないだろうか。儒教の限界とはこの辺りにあるのだろうと思う。
儒教的な身分制と道徳の縛りから解放されたらどうなるか。蓋をされて押さえつけられていた内奥の情動が一気に噴き出してくるのではないだろうか。道徳で無理に抑えつけていたから逆に反道徳的な情動を生み出し、欲望に突き動かされて反道徳的な行動へと人を駆り立てるのだろう。儒教の歴史が古い中国において道に平気でゴミを捨てたり、暴徒化した群衆がスーパーなどに押し入って商品を強奪する光景が日本のマスコミによって報道されているが、そうした姿は社会主義国家になったからというのではなく、儒教がもつ限界が露呈したからだと思う。が、日本のマスコミのほとんどは戦前の体制翼賛報道機関にまで堕落しており、中国を仮想敵に見立てて排他的で国粋的なナショナリズムを煽るという任務を背負わされているのだから、そのまま鵜呑みにすべきではないだろう。意図的に誇張されている側面はあると思う(笑)。
その一方で、東日本大震災で被災した日本人が、物静かに整然と並んで配給させる食べ物を受け取っている姿をみた海外の記者が驚きの声を上げていたのを思い出す。海外にあってはこうした場合に、スーパーなどが群衆に襲われて商品を強奪されるのは当たり前だからだろう。この日本の現象を江戸時代からの儒教道徳の浸透と、明治維新国家によって、尊皇的に、そして国粋的にアレンジされた儒教道徳(=後期水戸学)である教育勅語のたまものだとみる識者がいたりするが、皮相的な見方であり大きな間違いである。わたしは日本という風土が育んだ性向だとみている。安倍晋三を初めとする政府与党の大方の議員達は、教育勅語を絶賛し、その復活を目論んでいるが、それは単なる国家権力に従順な臣民を作り出そうと悪巧みをしているに過ぎない。不道徳であり非倫理的な自民党議員の行為をみれば、儒教道徳を口にする権力者ほど道徳と倫理とは無縁であり、薄汚い性根をしている私利私欲の亡者だということが証明されているといえよう。
意外であるが日本に儒教が伝わったのは仏教よりも古く5世紀の初め頃といわれている。が、日本において儒教が歴史の前面に顔を出して権力と一体化したのは、それまで日本の儒教が陥っていた禅宗の教理への依存(儒釈不一)から儒教を独立させた藤原惺窩の高弟である林羅山を庇護した徳川家康が、体制を盤石にするために朱子学を統治装置として利用したことに始まる。つまり近世の江戸時代になってからだ。
丸山真男が『日本政治思想史研究』(東京大学出版会)で論じているように、徳川家康が儒教に目をつけたのは、戦国の世が統一され、徳川幕藩体制を盤石とし末永く安定化させるためには、厳格な身分制を前提とした上で身分に応じた人の道(=道徳)を説く儒教に利用価値を見出したからだろう。動態の世を静態の世に変えるために儒教という宗教が不可欠だったのである。
縄文人の心と精神に源流をもつ日本人の宗教的な心については、後ほど述べるつもりである。順序が逆になってしまうが、近世から幕末を経て明治維新国家体制が成立する過程で儒教が演じた歴史的役割を、仏教と国学と神道と絡めてざっと眺めてみたい。そして更に、戦前の日本ファシズムの成立において大きな役割を演じた教育勅語と一神教的国家神道の問題性を、儒教道徳(後期水戸学)との関係性からもみてみたい。
その前に、日本人の精神構造における二つの断層を語ってからそちらに入ることにする。
仏教の受容は権力を抜きにしては語れない。仏教の受容とは国家(西欧近代的意味での国家ではない)の庇護の下に国家の守護を目的にしたものだったのであり、当然に支配層のための仏教であり、民衆とは没交渉であったといえる。
わたしは日本人の精神構造は二重構造をしており、支配層の精神構造と民衆の精神構造との間には深い溝があると思っている。
儒教の伝来が仏教よりも古いという事実があるが、支配層が選択したのは仏教だということになるのだろう。どうして仏教を選択したのかという疑問が頭をもたげてくるが、日本人の心と精神の古層としてある宗教的なものが、仏教に通じていたからではないか、とわたしは思っている。通じているから、逆にいうと、日本に伝わった宗教の中で仏教ほど日本的な姿へと変容した宗教はないのではないだろうか。インド仏教とは違うし、中国仏教とも違っている。日本独自の仏教なのである。この件についても後で触れたい。
日本における仏教史をみると、一般的には鎌倉仏教によって仏教の民衆化がなされたように解釈されている。長い間わたしは、釈然としないものを抱いていたのだが、山折哲雄の『仏教とは何か』(中公新書)に接して疑惑が晴れた。山折哲雄は次のように論じている。
「法然や親鸞、道元や日蓮の仏教思想がそのままの形では民衆に伝わらなかったという点では、平安仏教を代表する最澄や空海の場合と何ら異なるところはなかった。(中略)
要するに鎌倉仏教の担い手たちは、いずれも知識人的宗教という性格を濃厚に保持していたということである。かれらの宗教思想はいまだ民衆化・大衆化の契機を十分につかんでいたとはいいがたい。世に受け入れられることのない突出したカリスマと、かれらを取り巻く少数のエリート信者たちの結合というのが、その偽らざる姿であった。これまでの仏教史の常識は、鎌倉仏教における『民衆化』という契機をあまりにも過大に評価してきたのではないだろうか。
そういう傑出したカリスマ(祖師)たちを中心とするエリート仏教の流れにたいして、他方に、仏教の真の意味における土着化の傾向が途絶えることなく静かに進行していた。それがさきにみたように、外来宗教としての仏教と山岳信仰との融合、そしてその結果としての山中浄土観や遺骨信仰の形成というもう一つの底流であった。そしてこの第二の流れと動きが、奈良時代の行基や平安時代の空也の活動と結びつき、さらに鎌倉時代の一遍などの民衆運動と不可分の関係を保っていたのである。
この第二の民衆宗教の流れは、なるほどさきにのべたエリート仏教の第一の流れのようには自覚的なものでもなく、自立的なものではなかった。そのうえもちろんダイナミックな思想闘争を展開したわけでもなかった。しかしながらこの第二の伏流はしだいに民衆のこころをつかみ、かれらの生活様式をすら左右するような浸透性を示すことになった。第二の流れがさきの知識人仏教の流れと並行しつつ、やがてこれと交錯し融合する勢いを示すようになったのである。法然や親鸞の民衆化と、道元や日蓮の大衆化がやってきたといってもよい」
長々と引用したのは、日本においては支配階級と知識的階級の精神構造と、民衆の精神構造には、深い溝があったと思うからだ。知識的階級は中国と朝鮮を経由して入ってきた舶来の宗教である仏教をいち早く取り入れ、独自に解釈しながら徐々に変質させていったのだろう。そして、支配層は仏教によって体制の基盤強化と守護とを祈願しながら、日本的に変質した仏教を体制の中へと取り込んでいったのだろう。但し、支配層が仏教によって民衆の心を思いのままに掌握できるなどとは思いもしなかったはずだ。
わたしは支配階級と知識的階級の精神構造と民衆の精神構造との間に断層をみるのであるが、更に民衆の中にも断層が存在していると思っている。それは縄文文化と弥生文化の間に横たわる断層である。この断層こそが日本人の宗教的な心を語るときに重要になってくると、わたしは確信している。この断層を原初的断層と呼びたい。
縄文人と弥生人は同じ人種のモンゴロイドに属しているが、古モンゴロイドと新モンゴロイドの違いがある。現代の日本人は古モンゴロイドと新モンゴロイドの混血であることが科学的に解明されているが、東北地方や沖縄は古モンゴロイドの名残りを多く留め、更にアイヌはより縄文人に近いとされている。このことから原初の日本には縄文人が居住し、そこに半島経由で大量に移住してきた弥生人によって日本が徐々に占拠されていったと考えられている。縄文人は狩猟採集を基本として雑穀類やクリなどの栽培を行っていたようだが、動植物の宝庫であるブナ林が分布している東北地方を中心として居住し、後から稲作文化を携えて渡ってきた弥生人は、稲作に適した北部九州から西日本に定住していたようだ。最初は棲み分けを行っていたのだろうが、半島経由で渡ってきた弥生人は国家の概念を持っていただろうから、徐々に統一国家の形成に向かうことは分かろうというものである。この過程で、日本列島の先住民である縄文人は辺境へと追いやられたのであろう。
こうして3世紀中頃から後半にかけて生まれたのが大和朝廷であり、646年の大化の改新によって成立した律令国家体制によって、わたしのいう原初的断層が歴史的に作られ、日本の先住民であり、日本の風土そのままを一万年にわたって生きてきた縄文人の歴史と、縄文人の心と精神を意図的に切り捨ててしまったのである。そして意図的に、日本の歴史の始まりを弥生時代にしてしまったのである。しかし、わたしは日本人の原初としての風土的な意味での心と精神とは縄文文化の中にあると思っており、日本の歴史の始まりが縄文時代であることは動かしようがない事実だと確信している。
蘇我入鹿を暗殺した中臣鎌足と中大兄皇子によって打ちたてられた天皇を頂点とする律令国家体制(中央集権的国家体制)を正当化するイデオロギーが『古事記』であり『日本書紀』であることは広く知られており、上山春平『神々の体系』(中公新書)などで解明されてもいる。そして、『古事記』の神代記の神話は、半島を経由して大量に移住してきた弥生人が縄文人に代わって日本を治める歴史を描いていることもまた解明されている。
『古事記』の神代記は、天津神(天照大神などがいる高天原の神の総称)が国津神(天孫降臨以前に日本にいる土着の神)を征服する神話として語られ、天照大神の命を受けたニニギノミコトが葦原の中つ国を治めるべく高天原から高千穂峰に降り立った(天孫降臨)ことが語られているが、このニニギノミコトこそが天照大神の孫であり、天皇の祖先とされている。したがって天皇とは絶対的な神である天照大神の子孫だとされて、神の直系という衣装を纏った天皇の権威が絶対化されることになった。これは神話の形を借りて、稲作文化を携えて朝鮮半島から大量にやってきた弥生人こそが日本の歴史の始まりであることを強制するものであり、それ以前の縄文人の歴史はばっさりと切り捨てられることを意味している。
この神話によって日本人の祖先は稲作農耕民族であり、弥生文化こそが日本人の心と精神のルーツであるかのような虚構が一人歩きを始めたといえるのではないだろうか。
この虚構は支配階級と知識的階級に向けたもので、民衆向けのものではないのは仏教が伝わった経緯と同じであろう。しかし、この虚構が民衆に向けられ始め、虚構を民衆の心に植え付けようとしたのが国学であり、実際に国家権力によって上から強要される形で洗脳教育が行われたのは明治維新以降である。縄文人の一万年の歴史を一日に見立てれば、一時間にも満たない前の話しでしかない。
二つの断層は日本人の心と精神とを考える上で重要なものとなるはずであり、特に原初的断層が持つ意味は、原初的断層をどうみるかで根底的な価値観がひっくり返るような重大なものだと思う。
原初的断層がどういう形で影を落としているのか、民俗学という学問をみればはっきりと分かる。
日本民俗学の祖である柳田国男は日本人の祖先を稲作農耕民族としてみており、祭りや習俗の起源と意味を稲作農耕文化との繋がりでみようとする姿勢があり、その姿勢を堅持するあまり歪んだ無理のある解釈を産み落としている。折口信夫も同様である。柳田国男が民俗学を新国学といったことから分かるように、日本民俗学とは、儒教や仏教といった外来の宗教や文化の影響を取り除いていった先で、日本人の純粋な心と精神、または宗教的な心に辿り着こうという学問であるが、国学が『古事記』の神代記を絶対化たように、日本民俗学も『古事記』の神代記から自由になれないのである。
それでもわたしは、原初的断層があっても、縄文文化に息づく原初としての日本人の心と精神は、現代の日本人の心と精神の古層に脈々と息づいていると思っている。何故ならば、日本という風土が育んだものであり、日本の風土と共に生きることによって朝鮮半島から大量に移住してきた弥生人の心と精神へも影響を及ぼさずにはいられないと思うからである。
その証左を江戸時代に生まれた里山にみることができる。
里山は弥生人の稲作農耕文化と、縄文人の縄文文化の心と精神とが融合して生まれたものだと思うからだ。これについては後述したい。
さて、日本の宗教に話しを戻すと、権力が民衆を射程に置いて宗教を利用したのは江戸時代になるまでなかったのではないかと妄想している。「思っている」と書きたいのだが、「妄想している」と書いたのはその根拠をもっていないからだ。わたしは学者でもなく評論家でもなく、単なる素人のブロガーなので(作家だとは自任している)、妄想と断れば批難を浴びることはないという不届きな魂胆が働いているからだ。妄想とは便利な言葉である(笑)。
ここで注意しなければならないのは、先にみたように仏教といえども広く民衆の心へと浸透した宗教というものとしてはなかったのであり、いわば日本には一つの宗教による支配はなかったといえるのではないだろうか。だから逆にいうと、一つの宗教による徹底した支配がなかったから宗教的な心が息づいていたといえないだろうか。日本人はよく無宗教だといわれるが、それは一つの宗教を信じてはいないことにはなるが、だからといって宗教的な心がないということを意味してはいない、とわたしは思う。宗教は原初としての宗教的な心から始まって、原初としての宗教的な心から遠ざかることで解釈学としての宗教として発展するものだと思うが、そうであれば原初としての宗教的な心が息づいていることの方に、わたしは目を向けたいし、また重視したい。
一つの宗教による徹底した支配がなかったのは、偶然的なものなのか、それとも必然性があるのか、という問いは重要だと思う。わたしは必然性をみている。日本人の心と精神の古層に息づく宗教的な心が、一つの宗教に支配されてしまうことを拒んでいるのだと思うからだ。では、その古層に息づく宗教的な心は、どうして宗教へと結実しなかったのか。この問いもまた重要だと思う。古層に息づく宗教的な心は、解釈としての宗教にはなれない本質があるのであり、また解釈としての宗教になることを頑なに拒む性質のものだから、というのがわたしの仮説である。この件については最後に論じたい。
上述したように、徳川家康が朱子学を重用してからは、徳川幕藩体制を支える宗教は儒教ということになるのだろうが、士農工商という身分制を敷き、それぞれの身分に応じた道(道徳)を極めることを求めたが、この身分制に応じた道が縦関係の道徳だとすれば、士農工商の横関係にもまた厳格な道があるのである。君臣・父子・夫婦・長幼・朋友の道徳がそれである。こうした縦横の関係に道徳をはめ込んでいるので民衆の生活にも儒教的な道徳は色濃く影を落とすことになるはずだが、影響は否定はしないが、やはり儒教は支配者(=為政者)のための道徳という側面が根強くあるのではないだろうか。だから宗教という匂いが希薄となっているのだ。武士道にはなり得ても、民衆の心までも吸い寄せる宗教にはなり得ないのである。
表向きは儀礼を重んじても、腹の中ではあかんべーをしていたのだろう。儒教の限界と弱点が、江戸時代の日本にあってはあからさまだったのである。したがって近世の儒教は、ほとんど宗教の体裁をなしていなかったのではないだろうか。儒教が権力と一体化していても、それは宗教という意味での一体化ではなかったのだろう。しかし、宗教的な装いはしていたことだけは確かだと思う。
この儒教の在り方と歩調を合わせるかのように、仏教もまた宗教的な色彩を弱めているのは面白い現象だと思う。仏教の宗教色を弱めさせたのは支配層である。
山折哲雄編『日本人の宗教とは何か』(太陽出版)の中で、「第5章 江戸時代」を担当した島田裕巳が示唆的なことを論じている。近世は世俗化した時代だというのだ。仏教は広く民衆の心の中にまでは侵入できなかったことを先に述べたが、仏教は教団として自らが権力を奮う勢力でもあったのは事実である。島田裕巳は「比叡山延暦寺と石山本願寺が焼き討ちされ、その力がそがれたあと、新来のキリシタンもまた禁制となり、社会的な影響力を失った。この一連の動きは、宗教的な権力がその力を失い、世俗的な権力の支配下におかれたことを意味する」と論じている。
どうも島田裕巳は宗教学者だからか、宗教に過大の期待をしているような感じを受ける。「宗教的な権力がその力を失い、世俗的な権力の支配下におかれたことを意味する」という中に、島田裕巳の宗教に向き合う本質的姿勢が垣間見えるのである。国家権力と宗教とを対立的にみる視線である。わたしの視線は島田裕巳とは真逆で、国家権力と宗教とを対立的にみていない。歴史は宗教が国家権力と癒着したり、一体化したり、また宗教自体が国家権力そのものになったりしたことを語ってくれている。むしろ、宗教が国家権力と真正面から衝突するのは例外的事例だと考えている。その例外的事例においても、宗教の衣装を纏った権力と、国家という衣装を纏った権力との衝突だと捉えている。宗教と国家という衣装を剥ぎ取れば、権力と権力の衝突にすぎないのではないだろうか。
わたしがこうした捉え方をするのは、宗教的な心と宗教とを切り離してみているからだ。島田裕巳はオウム真理教に過大な幻想を抱いたようだが、その幻想を導き出した要因は、島田裕巳の宗教と国家権力とを対立的関係にみる視線にあるのだろう。だから宗教に可能性を夢想してしまうのだ。わたしはオウム真理教とは、宗教の衣装を纏った麻原彰晃の私利私欲と権力欲そのままに洗脳された集団とみなしているので、初めから宗教的な心のない麻原彰晃が生み出したオウム真理教に何の期待もなければ、宗教ですらないと思う。この意味ではIS(イスラム国)に通じている。
問題なのは、どうしてオウム真理教やIS(イスラム国)へと若者たちの心が吸い寄せられていったかという点だろう。そして、どうしてオウム真理教とIS(イスラム国)のようなおぞましい化け物を社会は産み落としたのかという点だろう。若者たちの心が吸い寄せられていくからといって、オウム真理教とIS(イスラム国)に可能性があるのではない。また可能性を見出すとしたら、よほどの宗教音痴である。
確かに戦前に日本ファシズム国家によって弾圧された大本教のような特異な例はある。そして、織田信長に抵抗した比叡山延暦寺や加賀の一向宗門徒のような例もある。しかし、わたしはこうした例も、基本的には、宗教の衣装を纏った権力と、国家という衣装を纏った権力との衝突だと捉えている。
僧兵をもつ比叡山延暦寺は宗教的権威で守られた治外法権的な権力であった側面がある。また朝廷との繋がりもあった。自らが絶対的な神となろうとしていた信長にとっては宗教的権威とは邪魔でしかなく破壊すべき対象だったのだろう。比叡山と同じく加賀の一向宗門徒も信長に反旗を翻したが、一向宗門徒の世界においては自らが信じる宗教的権威こそが絶対なのである。そうした意味においては、極論すれば、織田信長という全国統一へと向かう権力に逆らっただけで、浄土真宗本願寺教団という宗教的権力には絶対服従だといえるのではないだろうか。
たとえば創価学会であるが、戦前はファシズム国家権力から弾圧され、教団の創設に深く関わった牧口常三郞が治安維持法で投獄され獄中死している。その創価学会が、戦前のファシズム国家体制への回帰を掲げる安倍政権へと擦り寄り、その露払い役にまで堕落している現実がある。現代版の治安維持法といわれる特定機密保護法を率先して推進し、平和憲法護持を基本とした創価学会という教団と一体となった公明党があろうことか、集団的自衛権を認める安保法制成立に深く関わり強行採決までしたのである。
創価学会を眺めただけでも宗教とは何か、と考えざるを得ない。そして、宗教そのものを疑わざるを得なくなる。
教団が真逆の方向へと歩き出したのに、その教団の内部にいる信徒が異議を差し挟むことがないのも不思議である。おそらく、異議を差し挟むことができない雰囲気が教団を支配しているのだろう。また教団を絶対的に信じ切っているのであろうから、教団の行為と教団が歩いて行く方向性を客観的に観て判断する目と理性とを奪われてしまっているのだろう。いわゆる宗教的洗脳である。
教団という組織が上意下達の絶対的ヒエラルキーによって貫かれているのではないだろうか。したがって、信仰とは教団上層部の意向を神の声として崇めて無条件に従うことであり、教団の存続と発展のために滅私奉公することが日常的な信仰活動となってしまっているのではないだろうか。
滅私奉公といっても、完全な滅私ではない。絶対的ヒエラルキーの中で、己の地位を高めるための奉公であり、自分の存在と正当性を得るための奉公であり、だから奉公に生き甲斐を見つけ出すことになるのだろう。
新興的な宗教的教団とは、一般的な社会とは異質な世界を持っている。宗教的教団が形成されていく過程では、社会と異質な信仰によって形成される共同体的世界を演出することで、民心を惹き付けていくのではないだろうか。社会の中から弾かれたり、社会の中に居場所を見つけられなかったり、社会の中で差別されたり、生活苦のどん底に突き落とされたり、病魔に冒されたりして、社会と人生に絶望しながら這いずり回るようにして孤独を生きている人々に手を差し伸べて、そうした社会とは切れた別の世界があることを説くのだと思う。
こうした信仰が宗教といえるのだろうか。そして、一人の人間として考えたとき、宗教的な心とはそうしたものでいいのだろうか。わたしは素朴な疑問を持ってしまうのである。宗教的な心から出発したはずが、宗教という姿へと徐々に変質していく中で、宗教的な心とは似て非なるおぞましい姿へと脱皮していまうのではないだろうか。
創価学会だけでを言っているのではない。
幕末から明治維新にかけて生まれた神道系の宗教団体は、大本教を除いて(大本教から分離して、一神教的国家神道の権化となった教団も誕生している)ほとんど国家権力と一体となり、一神教的国家神道を掲げて排外的ナショナリズムを民衆に植え付ける機関とまでなっていったのが歴史的事実である。
終戦直後はなりを潜め巧妙に姿を隠していたが、またしても国家権力と癒着し、安倍晋三を祭り上げて歴史の表舞台へと立ち現れてきている。そして、戦前と同様に排外的で偏狭的なナショナリズムを煽っているのである。
宗教の持つ威力(正の利用価値)と、その反対に、宗教の持つ破壊力(負の利用価値)に権力者は敏感である。宗教と権力が一体であることを知っているから、豊臣秀吉と徳川家康はキリシタンを弾圧し、キリスト教の布教を禁止したのだろう。キリスト教と一体となった西欧の権力の意志を肌で感じられるのである。織田信長がキリスト教の布教に寛容だったのは、キリスト教によって日本における宗教的権威を相対化するつもりだったのではないだろうか。いずれは自分自身が神になるのであり、そのときにはあらゆる宗教の権威を認めることはしなかったはずだ。もしくは、信長という権威をより強くするために利用するつもりだったのかもしれない。
島田裕巳を批判したが、島田裕巳の宗教の見方は大方の宗教学者に共通しているものなのだろう。
宗教学によれば宗教とは自然宗教と創唱宗教に分類されるようだ。宮家準は『日本の民俗宗教』(講談社学術文庫)の中で、「創唱宗教はキリスト教、仏教、イスラム教などのように、深い宗教体験のなかで啓示や悟りを得た教祖がそれをもとに開教したものである。そして世界の人類全体を信者にすることを目ざしているゆえ、世界宗教ともよばれている。創唱宗教の教祖は釈迦が出家して修業し、イエスがユダヤ教の律法を否定したように、既存の社会秩序にもとづく自然宗教を超克することによって成立する。それゆえ、当初の信者は自然宗教では救済が保証されない、差別され虐げられた人びとなのである。(中略)そのせいもあってか、創唱宗教は現世拒否的な傾向をとり、その救済も個人的なものである。そして救済されたと確信したあとは、その信仰が深く内面化され、それにもとづいた信仰生活に入り、布教活動に邁進するのである」といっている。
宮家準の創唱宗教の捉え方も、その始まりを反体制的な性向とみなしているので、島田裕巳の宗教の捉え方と通じたものなのだろう。
しかし、自然宗教が「既存の社会秩序にもとづく」ものとする宮家準の視点は、とても納得できるものではなく、自然宗教を「日常生活のうえでの現世利益の達成に重点がおかれてもいる。それゆえ、救済されれば御利益があるとして、しばしばそれにたよることがあっても、信仰を内面化していくことはあまり認められない」というに至っては、宗教学者の盲目的な創唱宗教信仰としかいいようがなく、自然宗教を皮相的にしか捉えられていないとしかいいようがない。自然宗教にも現世の御利益を求めるものばかりではないし、ごりっぱな体系的教典や教義といった頭でひねくり出したものがくっついていないから、純粋な宗教的な心が分かろうというものである。
創唱宗教の反体制的な要素が原初にあったとしても、宗教教団として成長する中で、全く違った化け物の貌を持つまでに変容してしまうのではないのか。そうでなければ、王権神授説など生まれようがないではないか。
ニーチェはキリスト教の本質はルサンチマン(弱者の反感)にあるとして批判したが、正しく宮家準の創唱宗教信仰はルサンチマンに発しているといえるのではないだろうか。
ニーチェの思想の神髄は、キリスト教そのものにニヒリズムをみていることであり、キリスト教の神が否定されたことでニヒリズムが世界に蔓延しているのではないのである。キリスト教の本質がニヒリズムを連れてきたのである。かくいうわたしも、ニーチェの思想を誤解していたのである(笑)。
ニーチェは「神はどこへ行ってしまった」といっている。神を殺したのは誰あろうキリスト教なのである。ニーチェは神を否定したのではなく、神を否定したキリスト教を否定したのである。
わたしはニーチェが求めた神に心当たりがある。が、この件については最後に触れたい。
話しが脇道に逸れてしまったので、島田裕巳のいう近世の世俗化した社会に戻りたい。
西欧近代主義とは政治の世俗化でもある。国家のあり方と方向性を決める政治を宗教的な権力と権威から切り離して独立させ、合わせて宗教的な倫理を私的領域に封じ込めることでもあった。西欧近代主義の政治の世俗化と社会の世俗化に引き寄せて、日本の近世の世俗化した社会を島田裕巳は次のように述べている。
「日本の近世社会は、徹底した『世俗化』とともにその幕を開けたとも言える。宗教的な権力が世俗的な権力の下におかれるという体制は、その後の日本社会における宗教のあり方を根本から規定することになった。
フランスにおいて、カトリックの宗教的な権力が世俗的な権力の下に組み込まれるのは、一七八九年の『フランス革命』以降のことである。フランス革命は、欧米における宗教と政治の関係に根本的な変化をもたらす先駆的な出来事であったが、日本では、その二百年近く前に、世俗的な権力の優位が確立されていた。日本は極めて早い段階で、世俗化が進んだ社会であり、そこにこそ近世から近代にかけての日本人の宗教のあり方の第一の特徴が示されている」
島田裕巳は重大な点を見落としている。
西欧近代主義の理念の幕開けを告げるフランス革命は、宗教の支配と呪縛から国家を切り離しただけでなく、国家と個人の関係性を明確にしたことであり、その前提にフランス人権宣言として謳われた人は生まれながらにして自由と平等と幸福追求の権利を与えられているという天賦人権論(自然権)がある点である。そして天賦人権論を踏まえた上で国家との関係性を明確化した社会契約説に立っている。
日本の近世社会の世俗化に天賦人権論と社会契約説の視点はない。西欧的意味での自然権という権利をもつ個人という概念も自覚もないのである。西欧近代社会の世俗化と日本の近世社会の世俗化とは異質なものだといえる。
島田裕巳のいう近世社会の世俗化とは、国家権力が如何なる宗教的権力からも束縛されず、国家権力にとって脅威になるような宗教的権力を実質的に解体し無力化したことを意味するのだろう。宗教の本質を既成の権力と対立的なものとしてみる島田裕巳の視点からみれば、日本の近世社会は正しく世俗化した社会だといえる。
しかし、逆接的にいうと、国家権力にとって脅威になるような宗教的権力を実質的に解体し無力化したから、特に仏教が民衆の生活の中に根を張ったともいえるのではないだろうか。知識的階級によって独占的に解釈されていた仏教の大衆化といえるのだろう。山折哲雄のいう第二の民衆宗教の流れに仏教が飲み込まれたと言い換えられるのかもしれない。
近世が果たした仏教を中心とした宗教の大衆化と世俗化が、現代の日本社会の宗教的な基礎を作り上げているようである。そして、現代にも受け継がれている宗教的な慣習や風俗や文化の源流でもあるようだ。山折哲雄は仏教と神道の「国民宗教化」といっている。
今回で終わりにしようと思っていたのだが無理のようだ(笑)。
今度こそ次回は終わりとするつもりだ。儒教の限界を看破した国学が、その限界を超えるべく神道をどう改良して、あのおぞましい一神教的国家神道を作り上げていったか。そして明治維新国家がその一神教的国家神道を更に手を加えて体制の根幹へと据え、国家自らによって生み出した一神教的国家神道という国家宗教による統治を行うという、世界に例を見ない壮大な実験の結果はどうなったか、みてみることにしたい。壮大な実験の過程において、雨後の竹の子のように次から次へと生まれた新興宗教は国家宗教へと自ら率先して隷属していくのであるが、その浅ましい姿こそ宗教の本質を炙り出しているのではないだろうか。
もう一度断っておくが、私はこうした宗教を否定するものであるが、だからといって宗教的な心を否定するものではない。ニーチェが「神はどこへいったのか」といって神を求めたが、その神は西欧的精神土壌における神の姿とは全く異質な姿をして、日本という風土そのものである縄文の森にいると思っている。一神教的国家神道とは、日本という風土とは真逆のもので、むしろ西欧的精神土壌の産物であるともいえ、日本人の原初としての心と精神とは無縁のものである。だから安倍晋三のような私利私欲に塗れ汚れきった皮相的な心を生きる人間が、恋い慕うものなのである。
いずれにせよ、安倍晋三は権力としての宗教と縁があっても、宗教的な心とは無縁の男である。
次回にご期待あれ(笑)。
※小説はキンドル版の電子書籍として出版しています。
※Kindle版電子書籍は、スマホとPCでも無料アプリで読めます。